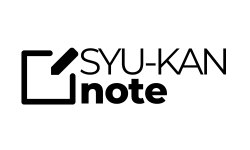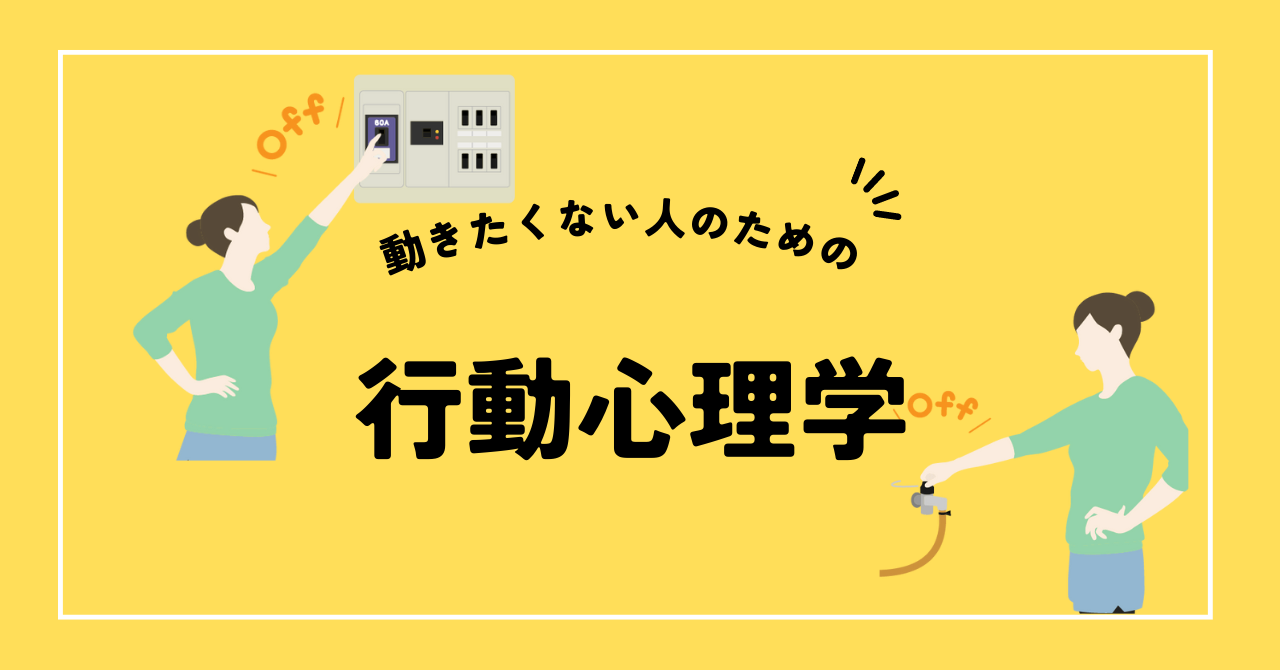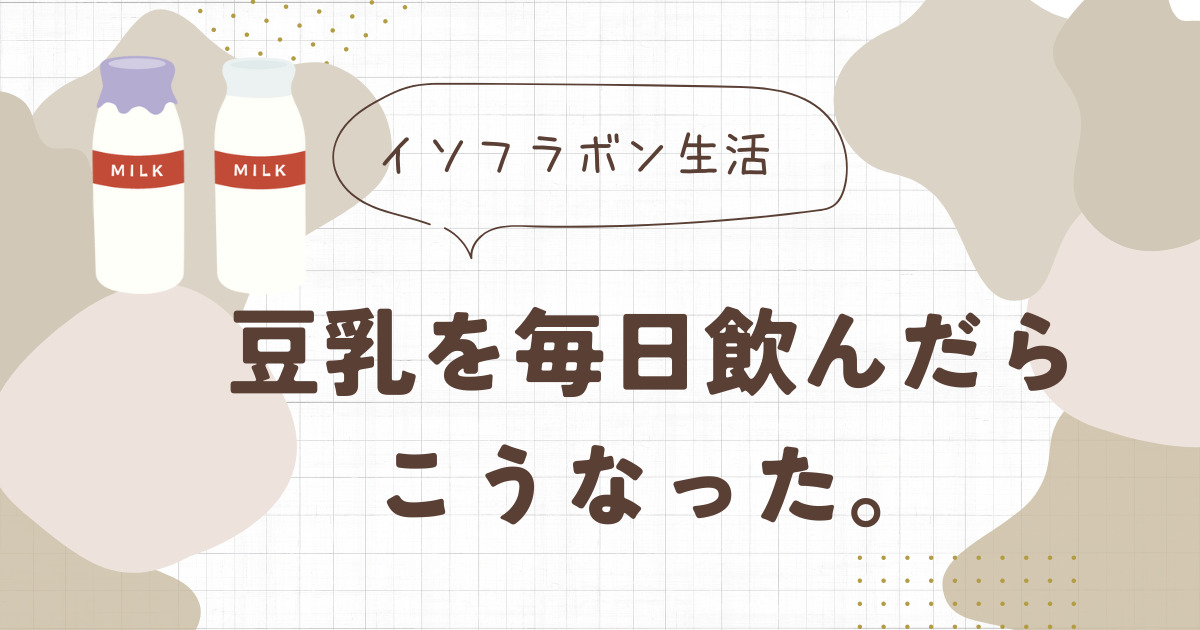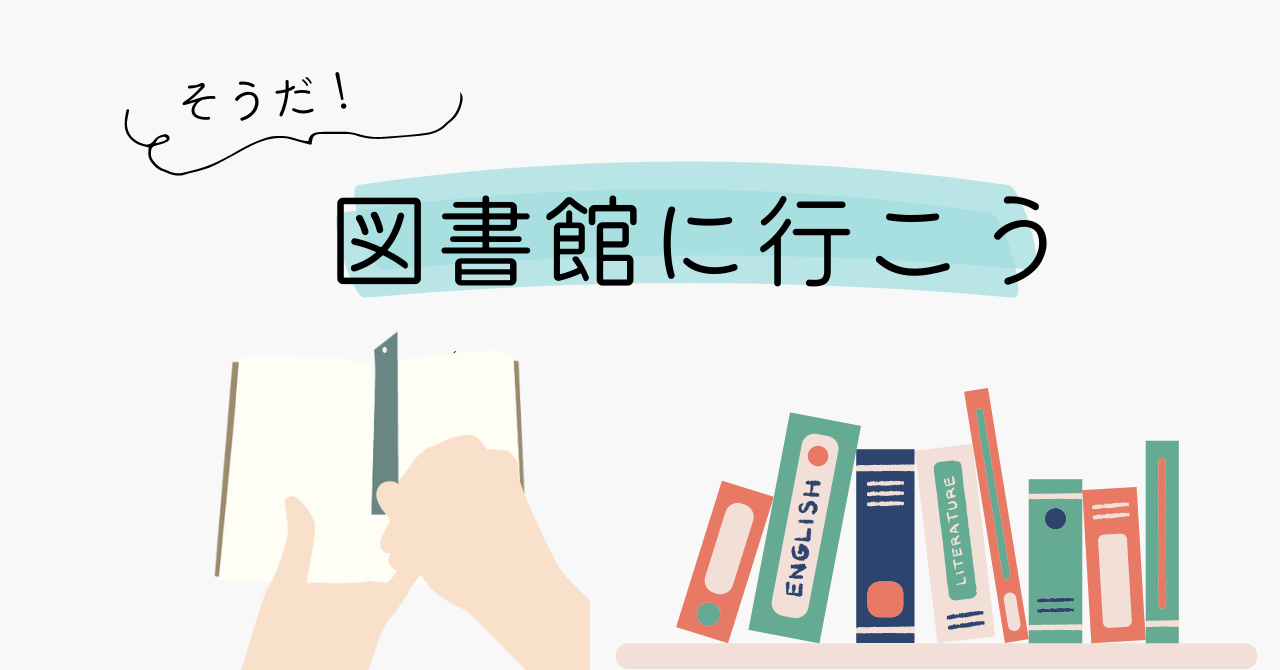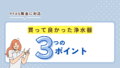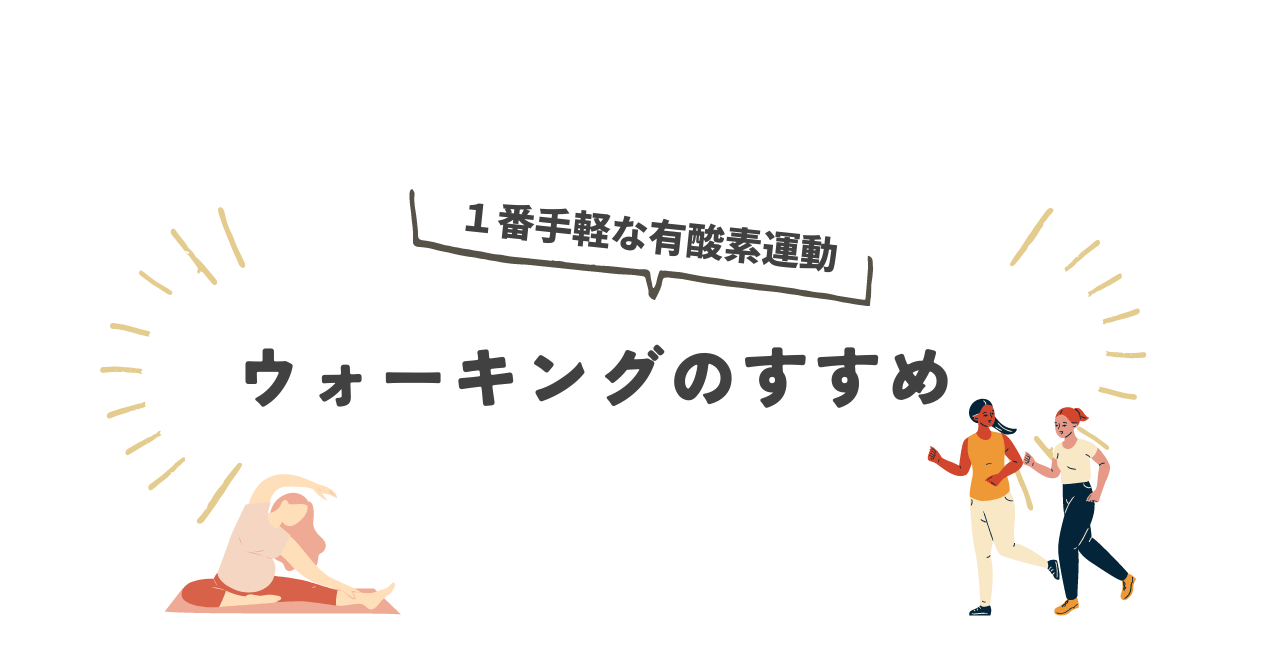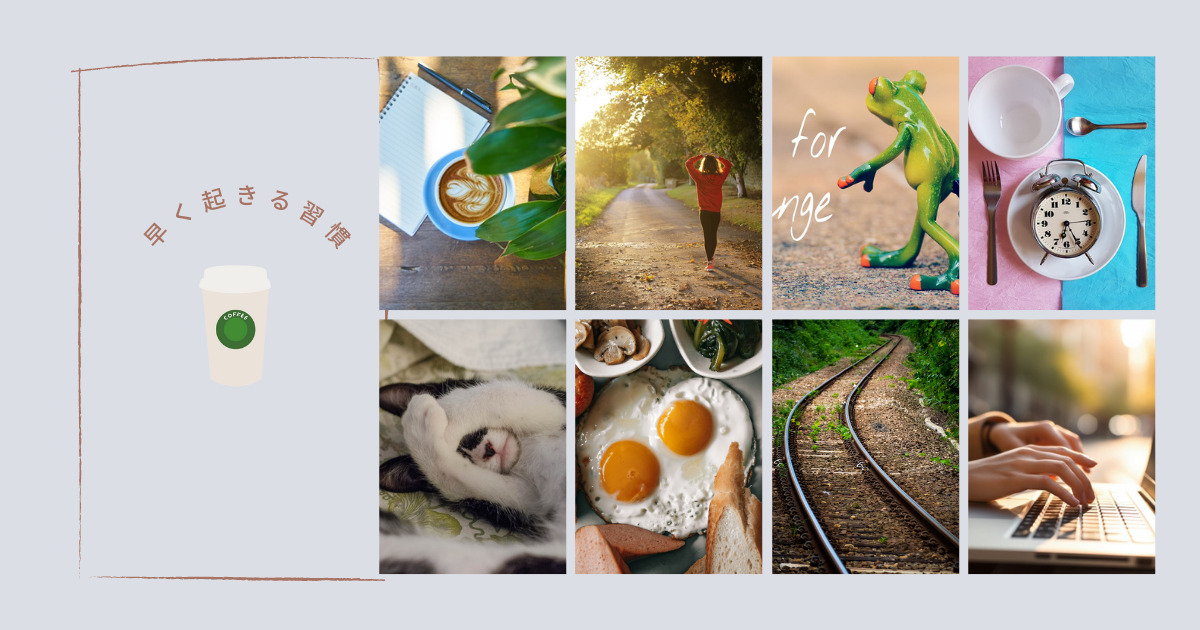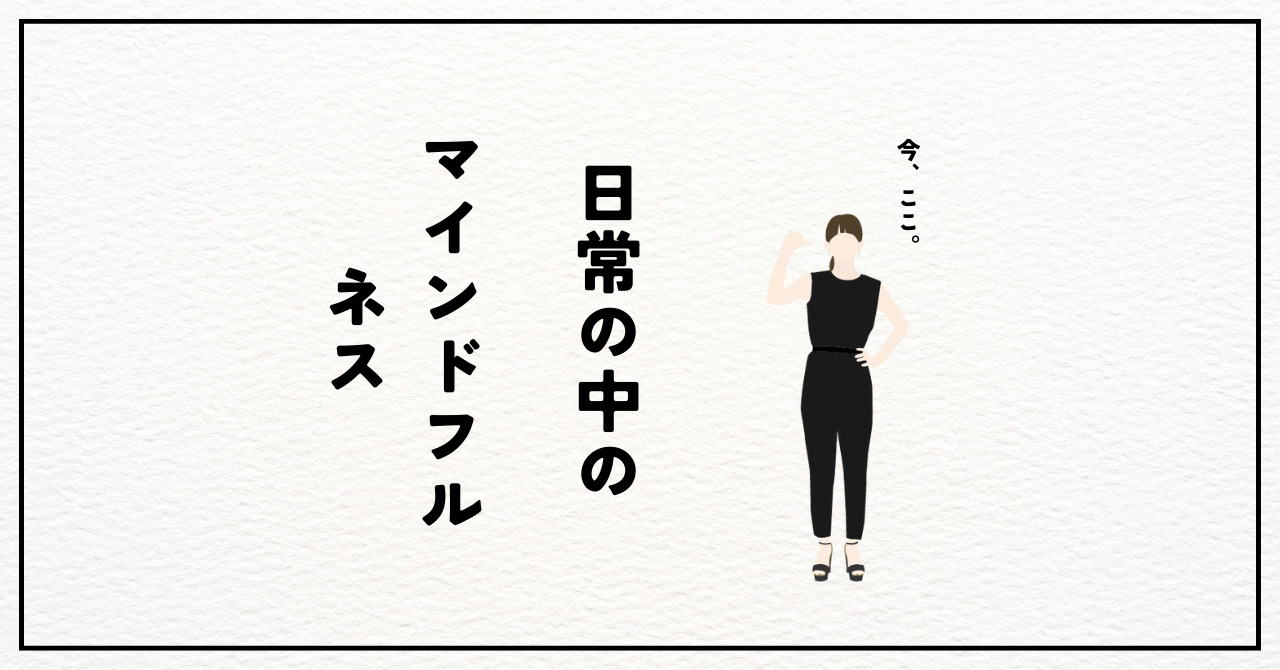「何もしたくない」「動きたくない」と感じることは、誰にでもあります。
そんなとき、「自分はダメだ」と責める前に知ってほしいのが、行動心理学の考え方です。
実は「動きたくない」と感じるのは、あなたの心と体が出している立派なサイン。
この記事では、50代一人暮らしの私の実体験を交えながら、「なぜ動けないのか?」「どうすれば一歩踏み出せるのか?」をわかりやすく紹介します。
もくじ
なぜ「動きたくない」と感じるのか?
① はじめの一歩が“ぼんやりしている”と人は動けない
行動心理学では、「人は先の見通しが立たないと、動き出しにくくなる」と言われています。
何かを始めようと思っても、「最初に何から手をつけていいかわからない」「全体像が見えない」状態だと、脳はストップをかけてしまいます。
たとえば「旅行に行こう」と決めたとき、まず何を調べて、どこで予約をして、持ち物は何か…といった一連の流れが見えていないと、どんどん億劫になります。
逆に「このサイトで予約→この日程でチケット→荷物はこれ」と手順が見えてくると、自然と体が動き出します。
つまり、「動きたくない」の正体は“面倒くささ”というより、次に何をすればいいか不明確なことが原因なだけ、なんてことも多そうです。
② 心に余裕がないと、行動のハードルが上がる
忙しい時期やストレスが多い環境では、脳の処理能力が落ち、「めんどくさい」と感じやすくなります。
私も過去、接客業で対応に追われていた頃は「誰とも話したくない」「一ミリも動きたくない」と感じていました。
この“何もしたくない”状態は、決して甘えではなく、脳のキャパオーバーによる自然な反応です。
”ワクワク”するってどうゆうことですか?
疑問を持たない(持てない)
私は20代前半頃に、まったく好奇心というものがなくなってしまった時期がありました。
仕事でストレスが重なり自分では解決の術がないように感じ、心を閉ざすことが唯一の自分を守る方法だったのだと、今にしてみれば思います。
この好奇心がほとんどない、という自覚がある人は案外多いのではないでしょうか?
生まれつき好奇心がないというのは考えにくく、恐らく幼少期の出来事や思考パターンが関係していると思います。
“ワクワク”するが理解できない心理
よく「ワクワクするかしないかで選びましょう」みたいな思考法があります。
でも”ワクワク”って、具体的にはどういうこと?と思う方もいるかと思います(私もです)
端的に言えば、高揚感や期待感があり、未来が楽しみで落ちつかないといったことです。
昔は恐怖や心配で胸が騒ぐ、という意味にも使われていました。
まさにこっちの心理の方が、個人的には良くわかります。
心を揺さぶられるのが昔から大嫌い、緊張や予期せぬ事態なってもてのほか。
でも、”ワクワク”という言葉が高揚感と恐怖感と近い感情がゆえに、どちらの意味でも使われていたと知って納得しました。
私は、”ワクワク”を緊張や心配ごと、恐怖と捉えていたんですよね。
同じ”ワクワク”でも高揚感や期待感、つまり興奮や刺激と捉える人がいるということなんですね。
疑問を持つことが好奇心の第一歩
日々の中で、「まてよ、本当か?」「そうだっけ?」みたいな疑問ってどうしていますか?
スルーしますか?
別に大したことじゃなくても全然良くて、私はとりあえず検索します。
疑問がわく、というのは好奇心の大事な芽だと思うからです。
そしてなぜ疑問に思うかという心理を自分なりに深堀していけば、興味の小さな芽から花が咲くこともあるはずだからです。
自分は好奇心があまりない、と思っている方でも、大多数の人の興味があることに惹かれないだけだったりします。
ほんの少しの疑問の種でも大事にしてみてください。
その疑問を解消させてやるという行為は、立派な知的好奇心です。
そこから大切にしていきたいですよね。
少しずつ動けるようになるために
① メタ認知を鍛える
「今、自分は疲れてるな」「余裕がないな」と、自分の状態を俯瞰して見る力が大切です。
これを意識するだけで、「じゃあ今日は少し手を抜こう」と選択肢が広がり、心がラクになります。
② 小さな行動を“できたこと”として数える
「お風呂に入れた」「洗濯物たためた」など、行動をポジティブにカウントしましょう。
自分を責めるのではなく、少しずつ“できた”を積み上げることで、自然と行動が増えていきます。
そんなこと?と思った方は「要注意」
心が病んだ時に、できなくなることが「お風呂に入る」ことだったりするのです。
③ 「終わり」を意識する:50代からの行動力のスイッチ
50代になると、身近な人の老いや死、健康不安など、「時間の有限性」を意識せざるを得ない出来事が増えてきます。
私自身も身近な人や、著名人の訃報に触れるたび、「今しかできないことって何だろう?」と考えるようになりました。
「あと何回、桜を見られるのか?」
「この体で動けるのは、あと何年か?」
そんな問いを自分に投げかけるだけでも、「今をどう使うか?」という視点が自然と生まれてきます。
人は「終わり」があるからこそ、動ける。
若いころより体力や集中力は落ちていても、経験や判断力がある今だからこそ、“自分のために動く理由”がよりリアルに感じられるはずです。
行動できる人の特徴(行動心理学的アプローチ)
- 気になったらまず“やってみる”
- 完璧より「まず動く」ことを重視
- 人の目より「自分の好奇心」を優先
- わからないことはすぐ調べる
こうした人たちは、「疑問→行動」までのスピードが速いのが特徴です。
私も「気になることは、まず検索」から始めて、行動に少しずつ弾みをつけるようになりました。
おわりに
動きたくない日は、誰にでもあります。
でもその裏には、「本当は動きたいけど、何からやればいいかわからない」「心に余裕がない」など、いくつもの理由があるはずです。
行動心理学は、そうした“もやもや”の理由に光を当て、自分らしい行動のヒントを与えてくれます。
まずは今日、できたことをひとつ数えてみる。
それが明日、もっと動けるあなたへの第一歩です。